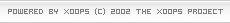現在、メインとしている研究分野は日本の現代物理学史であり、戦前から戦後まで、20世紀全体を対象としています。
長年取り組んでいた仁科芳雄についての伝記が『励起:仁科芳雄と日本の現代物理学』としてみすず書房から2023年7月18日に刊行されます。
日本の物理学史の研究は今後も続きますが、それに加えて次の三つの研究にも対象を広げています。
一つめは、科学と外交についての歴史的研究です。これは主に核物理学・原子力に関して行っているもので、一国内での研究開発の歴史から、複数国や国際的組織を対象としたトランスナショナルな知識生産を扱おうというものです。これについては、2021年に国際誌に二つの特集号を出しました。
二つめは、学術雑誌についての歴史研究です。これについては、2020年の初めに最初の総説論文が出ています。これを出発点にして物理学を中心とした日本の学術雑誌についての歴史研究を行う計画ですが、次の成果が出るのは少し先になると思います。
三つめは、知識生産のグローバル・ヒストリーです。これについては、現在は理論研究の段階です。